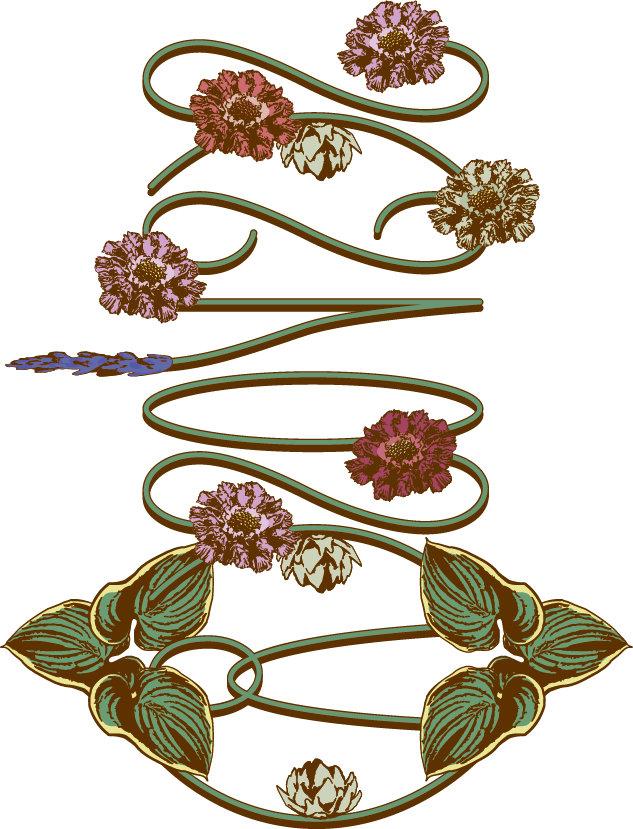- 「何無区」はどう読みますか?
-
「なんとなく(NANTONAKU)」と読みます。漢字の正しい読み方ではなく、造語です。フリガナは、「何(なん)無(とな)区(く)」ということにしています。
- 「何無区」はどのような活動をしていますか?
-
年に1回、ケンチCUBEや漢字建築を始めとした、何無区の作品を一堂に会した展覧会を開催しています。これは何無区の主軸としてとても大切にしていて、開催場所や開催規模を大きく広げることが夢の1つです。また、ここで発表される新作やこれまでの作品は、”物事屋”という何無区公式オンラインショップで購入できる仕組みになっています。それ以外にも、拠点近郊の販売イベントに出展したり、依頼があればケンチCUBEはワークショップ、漢字建築は講演会の形式で出張したりすることもあります。マンションリノベーションのお話やロゴデザインのお話をいただくこともあります。分野を問わず、とにかく色々なことに挑戦しています。
- 群馬と東京と新潟に拠点があるということですが、普段はどのように活動していますか?
-
週に1回、リモートでプロジェクトの進捗報告や、新たなプロジェクトの企画・相談をしています。各々の作業は、各自が自分のペース・自分の好きな場所で進めています。群馬県(高崎)に2人、東京都に2人、新潟県(長岡)に1人在住しています。
- どのような思いで建築をテーマにしたデザインスタジオ「何無区」の活動を始めたのですか?
-
建築デザインの魅力をたくさんの人に知って欲しいと思い、始めました。
「ケンチクデザインスタジオ」と名乗っているので建築設計事務所と思われることがありますが、私たちが魅力を感じている”ケンチクデザイン”は”建築物の設計”という解釈とは少し異なります。私たちは”大学で建築デザインを学んだ”という共通点があり、建築デザインが大好きなのですが、”建築物の設計がしたいわけではない”、という特殊な感覚も共通しています。
建物が出来上がるまでには多種多様な分野の協力が必要で、それらを束ねて1つの指針を打ち出し、解決に向けた選択肢を形にしていきます。そして同時に、建物が出来上がった後の未来の物語のことも真剣に想像し、考えをまとめていきます。「形が出来上がる前も、出来上がった後の未来のことも一生懸命に考えて良い」そこに私たちは建築デザインの魅力を感じました。過去も現在も未来も、自分たちの手でいくらでもデザインできると、建築が教えてくれたのです。そしてこの取り組み方を、建物を作ることだけではなく、様々な物作りや目に見えない事作り・場作りにも応用することで、より良い社会が実現できるのではないかと考え、何無区というスタジオを結成しました。
- 「漢字建築」とはどのようなものでしょうか?
-
漢字のシルエットをベースに設計された、架空の建物です。
展覧会では模型でご覧いただけます。鑑賞するだけでも十分楽しいのですが、各漢字建築の背景には解決が急がれる社会問題が隠れていたり、誰もが一度は夢見る憧れの生活が垣間見えたりと、少しばかり長く生きてきた大人ならではの楽しみ方も広がっています。
- 漢字の中を設計するというのは、どのようなきっかけで思いついたのですか?
-
ボケーっとしていたら思いつきました。
半分嘘ですが、パソコンで作業をしている時、何気なく視界に入っていた漢字が平面図に見えたのがきっかけだったと思います。そこから「漢字建築」という名前をつけて本格的に創作を始めるまで数年あるのですが、とにかくどんな表現の仕方でもいいから、楽しい建築を設計して世に出していきたいと必死だったことを覚えています。最近は”不動産のチラシで間取り図を見ることが好き層”や”図面って難しいと思ってた層”という、これまで建築議論の場をともにする機会がなかった人たちと建築について語り合う機会が生まれていて、漢字建築を世に出して本当に良かったと感じています。
展覧会で「漢字の意味と建築の用途は連動していないんですか?」と聞かれたことがあるのですが、元気よく「はい!」と答えました。おそらく「それでは漢字を利用する理由が本質的ではない!」という意見から生まれる問いかけだと推測します。建築デザインはそもそも複雑です。漢字の持つ意味や、そこに設計者の漢字に対する解釈まで織り込めば、漢字の意味に集中してしまい、漢字の中で繰り広げられている人間たちの営みや、現実の自分の生活と照らし合わせる想像の時間を失うでしょう。その複雑性の核は、その複雑さを心底楽しいと思える肩書きのある人間たちが集中すればよいと考えています。”複雑性があり日本人であれば大多数の人が知っている形”として、平仮名やカタカナを差し置いて、漢字をベースにすることに私たちは価値を見出しています。(※あくまでも展示鑑賞用に創作している漢字建築に対してです。オーダー漢字建築では捉え方が異なります。)
- ケンチCUBEはどのようなゲームですか?
-
チームで家づくりを楽しむボードゲームです。
配られたカードに書いてある部屋を順番に作っていき、みんなで1つの家を作っていきます。穴の空いたCUBEの穴を上手くつなげていくことで家が完成するのですが、これが意外と難しい..。だけど、子供から大人まで、年齢問わず遊ぶことができます。出来上がるお家の形は無限大なので、何度でも楽しめます。常日頃からボードゲームをプレイする方々は頭が本当に柔軟で、遊ぶ度に新たなルールや楽しみ方を見つけてくれていて、感動します。手にしてくださった皆さんの知恵もお借りしながら、より楽しく、より建築を遊べるゲーム開発を志しています。
- ケンチCUBEを開発した狙いはありますか?
-
友人と建築の展示会を訪れたときに、「全然わからない」とつぶやいていたことが印象に残りました。どんなに素晴らしい作品でもふだん建築に馴染みのない人には魅力が伝わりにくく、評価されにくいのかもしれないと感じました。
一方で、YouTubeのようなプラットフォームでは誰もが気軽に制作や発信ができ、視聴者も”いいね”や”コメント”で応えられる仕組みがあります。ゆえに次々に面白い企画が生まれ、YouTuberが憧れの職業になっている。”もし建築にも「誰もがつくれて、誰もが評価できる」そんな仕組みの場があれば、もっと多くの人が建築に親しみ、気軽に参加できるのではないか?”そんな思いが出発点となりました。
また”建築を考える”ことや”自分の住まいに思いをめぐらせる”ことは、本来とても楽しい時間のはずです。皆さんも一度は自分の理想のお家を妄想し、気持ちが高ぶった経験はないでしょうか?「建築を楽しむことは難しいのか?」と考えたとき、休日にマインクラフトを楽しむように、建築そのものを”遊び”や”趣味”として楽しめるものをつくりたいと思いました。
- 「建築をひらく」という言葉には、どのような思いがあるのでしょうか?
-
「子どもの自由な発想」も「主ふの暮らしに寄り添った工夫」も「建築家のアイデア」も、それぞれが等しく価値のあるものだと考えています。また建築には、”映画”や”音楽”、”スポーツ”のように、多くの人が楽しめるエンターテインメントとしての側面があるように思います。実際、レゴブロックやマインクラフトのような遊びは、建築に興味を持つきっかけとして大きな役割を果たしていると感じます。もし多くの人が建築に気軽に参加できるようになれば、議論はより多様になり、建築ももっと魅力的に育っていくと思います。
ケンチCUBEや漢字建築は、そうした「建築をひらく」ためのひとつの試みです。みんなで建築の面白さを共有し、みんなが建築を実践し、みんなが建築に感動できる。そんな未来が広がれば嬉しいなと思っています。
風邪にお気をつけて。(2026.2.26更新)